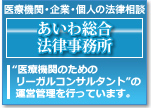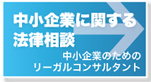判例解説
転送(医)義務認容事件
転送(医)義務認容事件
― 最高裁判所平成15年11月11日判決
【前提事実】
昭和63年9月29日、小学校6年生のXは、前々日から、軽い腹痛と頭痛・発熱が続いたため、医師Yが開設する医院(本件医院)でYの診察を受けた。Yは、上気道炎、右けい部リンパせん炎と診断し、薬を処方したが、改善がみられなかった。Yは、翌日も来診したXに対して、へんとうせん炎を病名に加え、前日の処方薬を2倍とする処方をし、10月3日に来院するよう指示した。
Xは、10月2日(日)、本件医院が休診のため、腹痛・嘔吐・吐気により、2度にわたり、E総合病院で救急の診察を受けている。
Xは、翌3日午前8時30分頃、母親に付き添われ、来診した。Yは、E病院での診療経過を聴いた上、急性胃腸炎、脱水症等と診断し、本件医院2階処置室のベッドで、午後1時頃までXに700㏄の点滴による輸液を行ったが、症状は改善されなかった。Yは、嘔吐が続くようであれば午後も来診するように指示をし、Xを帰宅させた。
その後も、Xは、嘔吐が続いたため、午後4時頃、母親に付き添われてYの診察を受け、母親に背負われて本件医院の2階へ上がり、午後8時30分ころまで700㏄の点滴による輸液を受けた。
Xは、嘔吐の症状が治まらず、点滴の途中で、点滴が1本目であるのに2本目であると発言したり、点滴を外すように強い口調で求めたりした。母親は、Xの言動に不安を覚え、診察を求めたが、Yは、外来患者の診察中であったため、すぐに診察せず、その後、点滴の合間にXを診察した。
Xは、午後8時30分頃、点滴終了後、母親に背負われて1階に下り、Yの診察を受けたが、椅子に座ることができず、診察台に横になっていた。しかし、熱が37.0℃に下がり、嘔吐もいったんは治まっため、午後9時頃、母親に背負われて帰宅した(以下、10月3日午後4時頃から同日午後9時頃までの間の診療を「本件診療」という。)。
Yは、Xの状態につき、症状の改善がみられなければ入院の必要があると判断し、翌日の入院の可能性を考えて、入院先病院あての紹介状を作成した。
Xは、帰宅後も嘔吐の症状が続き、熱も38℃に上がり、同日午後11時頃には、母親に苦痛を訴えたが、翌4日早朝から、呼びかけにも返答をしなくなった。Yは、同日午前8時30分頃、Xの状態が気になっていたため、X方に電話をかけ、容態を知って、すぐに来院するように指示した。
Xは、同日午前9時前頃、本件医院に来院したが、意識の混濁した状態で、呼びかけても反応がなかった。Yは、緊急入院を必要と考え、入院先を総合病院であるF病院と決め、上記紹介状を母親に交付した。
Xは、知人の車でF病院に行き、同日午前11時に入院の措置がとられた。F病院の医師は、頭部CTスキャン検査等を実施し、脳浮しゅを認め、当時の症状を総合して、ライ症候群を含む急性脳症の可能性を強く疑い、治療を開始したが、その後もXの意識が回復せず、入院中の平成元年2月20日、原因不明の急性脳症と診断され、Xには、急性脳症による脳原性運動機能障害が残り、身体障害者等級1級と認定された。
Xは、後遺障害は、Yが急性脳症等の初期症状を看過し、適時に専門の医療機関に転送しなかった過失によるものであるとして、不法行為による損害賠償を求めた。
第一審・第二審とも、X敗訴し、最高裁に上告。
【裁判所の判断(判例)】
「診療の経過にかんがみると、Yは、初診から5日目の昭和63年10月3日午後4時ころ以降の本件診療を開始する時点で、初診時の診断に基づく投薬により何らの症状の改善がみられず、同日午前中から700㏄の点滴による輸液を実施したにもかかわらず、前日の夜からのXのおう吐の症状が全く治まらないこと等から、それまでの自らの診断及びこれに基づく上記治療が適切なものではなかったことを認識することが可能であったものとみるべきであり、さらに、Yは、Xの容態等からみて上記治療が適切でないことの認識が可能であったのに、本件診療開始後も、午前と同様の点滴を、常時その容態を監視できない2階の処置室で実施したのであるが、その点滴中にも、Xのおう吐の症状が治まらず、また、Xに軽度の意識障害等を疑わせる言動があり、これに不安を覚えた母親がYの診察を求めるなどしたことからすると、Yとしては、その時点で、Xが、その病名は特定できないまでも、本件医院では検査及び治療の面で適切に対処することができない、急性脳症等を含む何らかの重大で緊急性のある病気にかかっている可能性が高いことをも認識することができたものとみるべきである。」
そして、「Yは、上記の事実関係の下においては、本件診療中、点滴を開始したものの、Xのおう吐の症状が治まらず、Xに軽度の意識障害等を疑わせる言動があり、これに不安を覚えた母親から診察を求められた時点で、直ちにXを診断した上で、Xの上記一連の症状からうかがわれる急性脳症等を含む重大で緊急性のある病気に対しても適切に対処し得る、高度な医療機器による精密検査及び入院加療等が可能な医療機関へXを転送し、適切な治療を受けさせるべき義務があったものというべきであ」るとし、「これと異なる原審の判断には、転送義務の存否に関する法令の解釈適用を誤った違法がある」として、原審の判決を破棄したが、転送義務を尽くした場合に結果を回避できたかどうか審理を尽くすよう、本件を原審に差戻した。
【ポイントの解説】
(1)転送(医)義務
最高裁判所は、医師が自ら医療水準に応じた診療をすることができないときは、医療水準に応じた診療をすることができる医療機関に患者を転送すべきであるとしており、これを転送(医)義務といいます。
別項でご紹介した未熟児網膜症事件に関する最高裁平成7年6月9日判決も、「新規の治療法実施のための技術・設備等についても同様であって、当該医療機関が予算上の制約等の事情によりその実施のための技術・設備等を有しない場合には、右医療機関は、これを有する他の医療機関に転医をさせるなど適切な措置を採るべき義務がある。」と判示し、転医義務を肯定しております。
その解説において、患者との診療契約により医療側が負う主たる債務は、その時点において当該医療機関に要求される医療水準を前提として、善良なる管理者の注意をもって適切な診療行為を内容とする債務であると説明しました。また、医療機関に要求される医療水準については、当該医療機関の性格や担当医師の専門分野等によって異なるということを説明しました。
この結果、患者に対する適切な診療行為が医療水準からみて一般開業医には妥当しないが、総合病院には妥当するという場合が出てきます。 このような場合に、患者を受け入れた一般開業医は、何ら対応しなくてよいかというと、決してそうではなく、そのような場合には、対応可能な医療機関に転送すべきであるというのが転送義務論であるといえると思います。
転医義務が生じる場面としては、①物的設備が不十分な場合、②人的体制が不十分な場合、③医師の対応能力が不十分な場合があると分析されています。
(2)転送(医)の具体的判断
医療側の過失については、医療水準で判断され、この転送義務についても、医療水準で判断するというのが最高裁判所の基本的な立場であると考えられています。
本件では、医師の転送判断が遅れたとして、それが転送義務違反と評価できるかが争われ、第1審・第2審が転送義務違反なしとしたのに対し、最高裁判所は、転送義務違反ありとしました。
そこでは、患者の病状に対する医師の判断の適否が問われているといってよく、自らの対応能力と患者の病状とを対照させた上で、自らは必要な措置をなし得ないという点の見極めが重要になります。 そして、一度転送義務が肯定されたのであれば、それは直ちに実行すべきこととなり、転送猶予の間に患者が急変すれば、医療側の責任が問われることになります。
なお、転送義務違反が肯定されると、生じた結果との因果関係も問題となりますが、この点については、次項でご紹介します。
(千賀 守人)