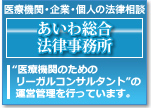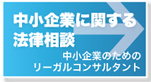判例解説
本人・家族に対するがんの告知
本人・家族に対するがんの告知
―最高裁判所平成7年4月25日判決ほか
【前提事実】
Aは昭和58年1月31日、B病院を訪れ、一般内科医師の指示で、2月9日、超音波検査を受け、胆嚢腫瘍の疑いありと診断された。
その後、コンピュータ断層撮影を経て、Aは印象として胆嚢癌と診断され、消化器内科のC医師は、3月2日、Aを初めて診察し、前記診察及び検査の結果を考え併せて胆嚢の進行癌を強く疑い、入院させ精密な検査をした上で確定診断と治療方針を決定しようと判断した。 しかし、Aの性格、家族関係、治療に対する家族の協力の見込み等が不明であり、右疑いを本人に直接告げた場合には精神的打撃を与えて治療に悪影響を及ぼすおそれがあることから、Aにはこれを説明せず、精密な検査を行った後に家族の中から適当な者を選んでその結果及び治療方針を説明することにした。
Cは同日、Aに対し、「胆石がひどく胆嚢も変形していて早急に手術する必要がある。」と説明し入院を指示したが、Aが3月22日から28日まで海外旅行の予定があること、仕事の都合及び家庭の事情などを理由に強い口調で入院を拒んだため、胆嚢も変形し手術の必要な重度の状態にあるから、仕事の都合を付け家族とも相談した上で入院できる態勢を整える必要がある旨を告げ、なお粘り強く入院を説得した。 その結果、Aが海外旅行後に入院するというので、Cはやむを得ずこれに同意し、入院の手続のため3月16日に来院することをAに約束させた。
Aは、同月16日、Cの診察を受けて4月11日以降速やかに入院する旨の予約手続をしたが、3月18日、Cに相談することなく、電話で応対した看護助手に対して家庭の事情により入院を延期する旨を伝えた。
Aは、予定通り海外へ旅行し、帰国後もCに連絡を取らず医師の診察を受けずにいたところ、同年6月病状が悪化して県立がんセンターに入院し、胆嚢癌と診断されて治療を受けたが、同年12月22日死亡した。
昭和59年7月、Aの遺族Xらは、Cは胆嚢癌の疑いがあると診断したにもかかわらず、AまたはXらにその旨を説明しなかったことが診療契約上の債務不履行にあたるとしてB病院を経営するYに対して損害賠償請求訴訟を提起した。
なお、昭和58年当時医師の間では、患者に対する病名告知に際して、癌については真実と異なる病名を告げるのが一般的であった。
原審(名古屋高裁平成2年10月31日判決)は、Aの職業、家庭環境、性格などが不明な段階では、胆嚢癌の疑いの告知がAに与える精神的・身体的打撃、AがCの説明を正確に理解できる可能性、治療に対する家族の協力の有無などについて予測不可能な状態にあったとして、控訴を棄却した。
【裁判所の判断(判例)】
(1)C医師にとっては、Aは初診の患者でその性格等も不明であり、本件当時医師の間では癌については真実と異なる病名を告げるのが一般的であったというのであるから、同医師が、前記3月2日及び16日の段階で、Aに与える精神的打撃と治療への悪影響を考慮して、同女に癌の疑いを告げず、まずは手術の必要な重度の胆石症であると説明して入院させ、その上で精密な検査をしようとしたことは、医師としてやむを得ない措置であったということができ、あえてこれを不合理であるということはできない。
もっとも、AがC医師の入院の指示になかなか応じなかったのは胆石症という病名を聞かされて安心したためであるとみられないものでもない。したがって、このような場合においては、医師として真実と異なる病名を告げた結果患者が自己の病状を重大視せず治療に協力しなくなることのないように相応の配慮をする必要がある。しかし、C医師は、入院による精密な検査を受けさせるため、Aに対して手術の必要な重度の胆石症であると説明して入院を指示し、2回の診察のいずれの場合においても同女から入院の同意を得ていたが、同女はその後に医師に相談せずに入院を中止して来院しなくなったというのであって、同医師に右の配慮が欠けていたということはできない。
(2)次に、Aに対して真実と異なる病名を告げたC医師としては、同女が治療に協力するための配慮として、その家族に対して真実の病名を告げるべきかどうかも検討する必要があるが、同医師にとっては、Aは初診の患者でその家族関係や治療に対する家族の協力の見込みも不明であり、同医師としては、同女に対して手術の必要な重度の胆石症と説明して入院の同意を得ていたのであるから、入院後に同女の家族の中から適当な者を選んで検査結果等を説明しようとしたことが不合理であるということはできない。そして、前記認定事実によれば、Aがその後にC医師に相談せずに入院を中止したため、同医師が同女の家族への説明の機会を失ったというのであるから、結果として家族に対する説明がなかったとしても、これを同医師の責めに帰せしめることは相当でない。
(3)およそ患者として医師の診断を受ける以上、十分な治療を受けるためには専門家である医師の意見を尊重し治療に協力する必要があるのは当然であって、そのことをも考慮するとき、本件において右の経緯の下においては、C医師がA及び上告人Xに対して胆のう癌の疑いがある旨の説明をしなかったことを診療契約上の債務不履行に当たるということはできない 。
【ポイントの解説】
(1)医療機関に課せられた説明義務については別項で紹介しましたが、医療行為について、十分な説明をし、患者の承諾を得るというインフォームド・コンセントが免除される場合として、一般に、①緊急事態、②同意能力の不存在、③本人・第三者に対する危険を防止するために医療行為を実施する必要性が認められる場合、④ありのままの説明が患者の健康や合理的な判断を損なうおそれが高いと認められる場合があげられます。
患者本人に対する癌の告知を避けた本件について、最高裁平成7年4月25日判決も、④の見地から、是認しました。
(2)但し、本件は、あくまで昭和58年当時の医療水準に照らした判断であることに留意しなければなりません。
近時の傾向としては、先進的医療機関を中心に、告知を求める患者には告知する傾向が強いというの当職の実感であり、例えば、国立がんセンター病院のがん告知マニュアル(平成8年9月)においては、「がん告知に関して、現在は、特にがん専門病院では『告げるか、告げないか』という議論をする段階ではもはやなく、『如何に事実を伝え、その後どのように患者に対応し援助していくか』という告知の質を考えていく時期にきている」とされています。
(3)平成2年から3年にかけての事案ですが、医師がステージⅣの肺癌患者本人に対して癌の告知は適当でなく、家族に説明する必要があると考えながら、説明の機会を逸したまま患者が死亡し、家族が末期癌の説明を早期に受けていればより多くの時間を患者と過ごすことができたとして訴訟提起した事案について、最高裁平成14年9月24日判決は、次のように述べました。
「医師は、診療契約上の義務として、患者に対し診断結果、治療方針等の説明義務を負担する。そして、患者が末期的疾患にり患し余命が限られている旨の診断をした医師が患者本人にはその旨を告知すべきではないと判断した場合には、患者本人やその家族にとってのその診断結果の重大性に照らすと、当該医師は、診療契約に付随する義務として、少なくとも、患者の家族等のうち連絡が容易な者に対しては接触し、同人又は同人を介して更に接触できた家族等に対する告知の適否を検討し、告知が適当であると判断できたときには、その診断結果等を説明すべき義務を負うものといわなければならない。
なぜならば、このようにして告知を受けた家族等の側では、医師側の治療方針を理解した上で、物心両面において患者の治療を支え、また、患者の余命がより安らかで充実したものとなるように家族等としてのできる限りの手厚い配慮をすることができることになり、適時の告知によって行われるであろうこのような家族等の協力と配慮は、患者本人にとって法的保護に値する利益であるというべきであるからである。」
(千賀 守人)