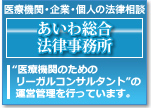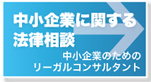判例解説
未熟児網膜症事件(医療水準)
熟児網膜症事件(医療水準)
―最高裁判所平成7年6月9日判決
【前提事実】
Xは、昭和49年12月11日、A病院で在胎31週、体重1508gの未熟児として出生し、同日午後、B病院に転医し、小児科に入院した。B病院のC医師は、同日、Xを保育器に収容して濃度30%以下で酸素投与し、同月21日まで、チアノーゼ発作等を認めた時には濃度を34~7%に上げたが、それ以外は28%前後の濃度の酸素を投与し、同日以降昭和50年1月16日まで21~28%の濃度の酸素を投与した。
Xの体重が2000gを超え、呼吸停止及びチアノーゼの症状がみられなくなったので、C医師は、同日、酸素投与を中止してXを保育器から出したところ、呼吸停止及びチアノーゼの症状を呈したため、再度保育器に収容し、同月23日まで24%前後の濃度の酸素を投与した。そして、C医師は、同日、酸素投与を中止してXを保育器から出したが、同月27日及び2月13日、呼吸停止及び全身チアノーゼを生じたので、酸素ボックスによる酸素吸入をした。
この間、Xは、昭和49年12月27日、B病院の眼科のD医師による眼底検査を受けたが、Xの眼底に格別の変化がなく次回検診の必要なしと診断され、その後、昭和50年2月21日の退院時まで眼底検査は全く実施されなかった。
Xは、退院後の3月28日、D医師による眼底検査を受け、異常なしと診断されたが、4月9日、同医師により眼底に異常の疑いありと診断され、同月16日、紹介先のE病院の眼科において、既に両眼とも未熟児網膜症瘢痕期三度であると診断され(Xの視力は両眼とも0.06)、B病院を開設したYに対して損害賠償請求訴訟を提起した。
原審(大阪高裁平成3年9月24日判決)は、Xが出生した昭和49年当時、光凝固法は有効な治療法として確立されておらず、治療基準について一応の統一的な指針が得られたのは厚生省研究班の報告が医学雑誌に掲載された昭和50年8月以降であるから、B病院が未熟児に対する眼底検査をし、本症の発生が疑われる場合に転医をさせていたとしても、担当医師において、未熟児に対し定期的眼底検査及び光凝固法を実施すること、あるいはこれらのために転医をさせることが法的義務として確立されていたものとすることはできないとして、B病院の責任を否定した。
X、最高裁へ上告。
【裁判所の判断(判例)】
最高裁は、被上告人Yは、診療契約に基づき、人の生命及び健康を管理する業務に従事する者として、危険防止のために経験上必要とされる最善の注意を尽くして上告人Xの診療に当たる義務を負担するとし、その注意義務の基準となるべきものは、診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準であるとしたうえで、診療契約に基づき医療機関に要求される医療水準について、次のように判示した。
「当該疾病の専門的研究者の間でその有効性と安全性が是認された新規の治療法が普及するには一定の時間を要し、医療機関の性格、その所在する地域の医療環境の特性、医師の専門分野等によってその普及に要する時間に差異があり、その知見の普及に要する時間と実施のための技術・設備等の普及に要する時間との間にも差異があるのが通例であり、また、当事者もこのような事情を前提にして診療契約の締結に至るのである。
したがって、ある新規の治療法の存在を前提にして検査・診断・治療等に当たることが診療契約に基づき医療機関に要求される医療水準であるかどうかを決するについては、当該医療機関の性格、所在地域の医療環境の特性等の諸般の事情を考慮すべきであり、右の事情を捨象して、すべての医療機関について診療契約に基づき要求される医療水準を一律に解するのは相当でない。
そして、新規の治療法に関する知見が当該医療機関と類似の特性を備えた医療機関に相当程度普及しており、当該医療機関において右知見を有することを期待することが相当と認められる場合には、特段の事情が存しない限り、右知見は右医療機関にとっての医療水準であるというべきである。
そこで、当該医療機関としてはその履行補助者である医師等に右知見を獲得させておくべきであって、仮に、履行補助者である医師等が右知見を有しなかったために、右医療機関が右治療法を実施せず、又は実施可能な他の医療機関に転医をさせるなど適切な措置を採らなかったために患者に損害を与えた場合には、当該医療機関は、診療契約に基づく債務不履行責任を負うものというべきである。」
そして、本件で、光凝固法の普及状況、B病院内での光凝固法の普及体制などを検討し、原審は、B病院の医療機関としての性格、XがBの診療を受けた昭和49年12月中旬ないし昭和50年4月上旬の兵庫県及びその周辺の各種医療機関における光凝固法に関する知見の普及の程度等の諸般の事情について十分に検討せずに医療水準を判断し、厚生省研究班の報告が医学雑誌に掲載された同年8月以前であるというだけで、当時において光凝固法は有効な治療法として確立されておらず、Bを設営するYに当時の医療水準を前提とした注意義務違反がないとした原審の判断には医療機関に要求される医療水準についての解釈適用を誤った違法があるものとし、Xの不服申立てにかかる部分につき破棄し、審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻した。
【ポイントの解説】
1)医療水準とは何か
医療水準とは、具体的な医療行為について医師の注意義務の存否を考える場合に、その判断のもととなる注意義務の基準をどの水準におくべきかという問題をいいます。
言い換えると、医療事故における医師の過失の有無を判断するための基準が医療水準であり、この点について、最高裁の先例は、「診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準」により過失の有無を判断すべきであるとしました(最高裁昭和57年3月30日判決)。
2)医療水準は一律に決せられるのか
最高裁昭和57年3月30日判決の後にも、この点に関する最高裁の判決が続き、「診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準」の意味について、最高裁は、全国一律に決せられるという見解を採用するものと理解されてきました。
ところが、本件で取りあげた最高裁判決は、本文をご覧いただけばお分かりいただける通り、そのような考え方を否定し、当該医療機関の性格や担当医師の専門分野等を考慮して医療水準を決するとしました。
平たく言うと、医療水準は、問題となった医療行為をした医師と同じ立場の通常の医師のレベルということになります。
これは、新しい治療法等特定の治療についての医学的知見が、①先進的研究機関を有する大学病院や専門病院、②地域の機関となる総合病院、③そのほかの総合病院、④小規模病院、⑤一般開業医の診療所という順序で普及していくことを前提として、当該医療機関と同じレベルの医療機関に普及する段階に至ると医師の注意義務になるということです。
一般的には、上記①ないし⑤の医療機関において受けられる医療のレベルに差があることははっきりしており、患者もそのことを前提として受診しているとされることから、本件で示された最高裁の判決は、支持されています。
3)医療慣行
医療水準に似て非なるものに、医療慣行ということがあります。これは、臨床の現場において、平均的な医師の間で広く慣行的に行われる方法をいいます。
医療慣行は、医療水準を判断するための1つの要素とはなりえますが、医療慣行に従って医療行為をなしたからといって、直ちに医療水準に従った注意義務を尽くしたということはできません。医療慣行は医療を取り巻く各種の社会的要因が決定するものであるのに対し、医療水準はあくまで医療の見地から医師が何をなすべきかという当為の観点から決定されるからです。
(千賀 守人)