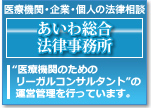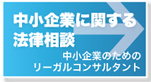判例解説
説明義務をめぐる諸判決
説明義務をめぐる諸判決
―最高裁判所平成13年11月27日判決ほか
【患者に対する説明が問題となる場面】
医療事件においては、医師の責任の根拠として、診療行為自体の過誤とは別に、説明義務違反の主張がよくなされます。ただ、一口に説明義務違反といっても、それが問題となる場面は様々です。そこで、まず、どのような場面で説明義務が問題となるのかを以下に見ていきます。
(1)侵襲的な治療について患者の同意を得る前提としての説明義務(治療方針の説明義務)
この点、最高裁平成13年11月27日判決は、「医師は、患者の疾患の治療のために手術を実施するに当たっては、診療契約に基づき、特別の事情のない限り、患者に対し、当該疾患の診断(病名と症状)、実施予定の手術の内容、手術に付随する危険性、他に選択可能な治療方法があれば、その内容と利害得失、予後などについて説明すべき義務がある」としています。
(2)病状についての説明義務
医師は、診療にあたって、まず患者の病状を把握し、それに応じて治療方針をたてなければなりません。の前提として、病状の説明をなすべきこととなります。
この点、最高裁平成14年9月24日判決は、「医師は、診療契約上の義務として、患者に対し診断結果、治療方針等の説明義務を負担する。」とし、診断結果(すなわち、病状)の説明義務を認めました(なお、この判決は、ガン告知に関する判決として、次項で紹介します)。
(3)転医に関する説明義務
医療機関に転医(送)義務が認められる場合については、別項でご紹介しますが、患者にはいかなる機関で医療を受けるかを自ら選択しうる権利(自己決定権)が認められますから、医師が自らの施設では対処困難と判断した場合には、医療機関は、患者に対し、その病状とそれに対する療法、当該療法を自らの施設では適切に実施しえないことを説明し、適切に実施しうる医療機関を教示して転医を勧告すべきであるとされます。
この点、最近の判決では、横浜地裁平成17年9月14日判決が、医療機関は「診療契約に基づき、人の生命及び健康を管理する業務に従事する者として、診療当時の臨床医学の実践における医療水準を基準として危険防止のために経験上必要とされる最善の注意を尽くしてAの診療に当たる義務を負担し」「被告センターがAの疾患に対し自ら適切な診療をすることができない場合には、上記診療契約上の義務を自ら履行することができないため、被告センター医師らは、代わって、必要に応じてAに対して適切な治療ができる他の医療機関に転医をするよう勧告するべき義務を診療契約上負担するものである」としています。
(4)医療行為の結果に関する説明義務
ある医療行為が終了しても、新たな医療行為を実施する必要がある場合は、(1)(2)(3)の説明義務の問題ととらえることができます。しかし、症状が固定したり、あるいは患者が死亡するなど新たな医療行為が必要とされなくなった場合、独自の考察を必要とします。
この点、東京高裁平成16年9月30日判決は、「病院の開設者及びその全面的代行者である医療機関は、診療契約に付随する義務として、特段の事情がない限り、所属する医師等を通じて、医療行為をするに当たり、その内容及び効果をあらかじめ患者に説明し、医療行為が終わった際にも、その結果について適時に適切な説明をする義務を負うものと解される」としました。
(5)医師付随情報の説明義務
最近では、上記の患者の病状や治療方針、それに関連する以外にも、医師の能力、医療機関の設備など医師に付随する情報についても、説明義務があるとされています。
この点、判決としてはちょっと古くなりますが、熊本地裁昭和52年5月11日判決は、治療行為の同意を得るためには、(1)で述べたところにとどまらず、「手術に伴う生命の危険性については単に一般的意味の危険性のみでなく、その施設における過去の実績についても判断の資料としてこれを説明する義務があるものと解するのが相当である」としました。
(6)療養方法の指導(結果回避)のための説明義務
(1)から(5)までみてきた説明義務は、患者の自己決定権に由来し、受任者は委任者に対し事の顛末を報告する義務を負うとする診療契約上の報告義務(民法645条)に根拠を求めることができます。
これに対して、ここで問題となる療養方法の指導のための説明義務とは、医師が自ら治療や観察をする代わりに、患者に治療や観察をさせるためになされる指示説明であり、その指示説明が不適切な場合には、医師自らが不適切な治療をしたり観察を怠ったに等しいものと評価されるというものです。
したがって、ここでの説明義務は、その限りで、患者の自己決定権とは無関係といえ、その違反は(1)から(5)までの説明義務違反とは性質を異にします。
【説明義務の内容・程度】
説明義務が肯定される場合、具体的にはどの程度(どのような)説明すべきであるかが問題となとなります。
この点、学説上は、
(1)医師の間の一般的慣行からして通常の医師が説明する情報を説明したか否かによるとする合理的医師説
(2)当該患者のおかれた状況に照らし合理的な患者なら重要視するであろう情報が説明されたか否かによるとする合理的患者説
(3)当該患者が重要視していたであろう情報が説明されたか否かによるとする具体的患者説
(4)具体的患者説を前提に合理的医師説を重畳基準とする二重基準説
が対立し、判例の立場は明確ではないとされています。
しかし、この点に関連し、最高裁平成13年11月27日判決は、乳がんを専門とする医師が、乳房切除手術を行うに当たって、乳房を温存することを患者が希望していることを知り、また、乳房温存術が当時の医療水準としては未確立ではあったが、それを実施している医療機関からはその有効性を報告する例が多いことを知っていたにもかかわらず、乳房温存術について説明しなかったことは、診療契約上の説明義務を怠ったというべきであるとしており、単純な①説②説③説には立たないことを明らかにしているように思われます。
【説明義務違反と賠償すべき損害】
民事損害賠償責任において、賠償されるべき損害の範囲は、義務違反と相当因果関係を有する損害に限られます。
そこで、例えば、患者の死亡という結果が生じた場合に、説明義務違反と死亡等との間で相当因果関係が認められないときには、説明義務違反というだけでは、死亡等に起因する全損害を賠償させられることはありません。その場合、賠償すべきは、説明義務違反により患者が被った精神的苦痛に対する慰謝料ということになります。
これに対して、説明義務違反が治療行為の内容を形成し(例えば、1(6)のケース)、説明義務違反と死亡等との間で相当因果関係が認めれるときには、死亡等による逸失利益及び慰謝料を含む全損害について賠償すべきこととなります。
(千賀 守人)