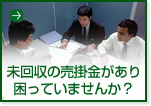従業員の管理
従業員はどのような場合に解雇できるか(解雇の実体的要件)
会社経営において、従業員との関係は避けて通ることができない問題です。
そこで、以下では、『解雇に関する問題』に関して触れます。
民法は、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる」(627条1項)と定めており、この結果、従業員の側からは、いつでも会社との雇用契約を解約(退職)することができます。
しかし、会社の側から、従業員を解雇することは、どんな場合でもできるというものではありません。一度従業員との間で雇用契約を結ぶと、従業員の地位は、労働法により保護されており、簡単に解雇できるものではないのです。
そこで、以下に、期間の定めをしなかった従業員との雇用契約において、どのような要件(事実)が存在すれば解雇が認められるのか、みていきましょう。
解雇事由の存在(就業規則ほか)
解雇とは,使用者が従業員の地位を一方的に失わせる行為(意思表示)であり,従業員の生活に与える影響は大きいものです。
そこで,法は解雇の事由に関する事項を就業規則に必ず定めておくべきものとし,会社が従業員を解雇するには,この就業規則に定められた解雇の事由が存在することが必要となります。解雇の事由は,会社が労働組合と締結する労働協約で定めることもできます。
もっとも,就業規則等に定められた解雇の事由は,例示列挙と解されていますので,「やむをえない事由」があれば,従業員を解雇することは可能です。
就業規則等に定める解雇手続の履行
就業規則や労働協約が従業員を解雇する際の手続を定めている場合には、その手続に従わなければなりません。
解雇予告手続の履行(予告除外認定を含む) 労基法20条
労働基準法20条1項は、「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」と定めており、従業員を解雇するには、30日前に予告するか、解雇予告手当を支払わなければなりません。
もっとも、同条項但書は、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。」としており、この但書が定める事由に該当すれば、解雇の予告や解雇予告手当は不要となりますが、この但書が定める事由に該当するかどうかは、労働基準監督署長の認定を受けなければなりません。
法律上の解雇禁止(法定禁止)に該当しないこと
労働法は、従業員の解雇を禁止し、あるいは制限する様々な場合を定めていますので、これらに該当しないことが必要です。
従業員の解雇が禁止され又は制限される場合としては、次のようなもののがあります。
- 不当労働行為となる解雇の禁止(労組法7条)
- 業務上の負傷疾病による休業、産前産後休業中及びその後の30日の解雇禁止(労基法19条)
- 国籍、信条等を理由とする解雇の禁止(労基法3条)
- 監督機関等に対する申告・申出を理由とする解雇の禁止(労基法104条、安衛法97条、個別紛争解決法4条3項、派遣法49条の3第2項等)
- 女性であることを理由とする解雇の禁止(均等法8条1項)
- 女性の婚姻、妊娠、出産を退職理由と予定した定めの禁止(均等法8条2項)
- 婚姻、妊娠、出産、産休、育児・介護休業を理由とした解雇禁止(均等法8条3項、育休・介護法10条、16条)
- 労基法等の手続保障についての不同意や過半数代表者への不利益取扱いの解雇禁止(労基法38条の4第1項6号、同施行規則6条の2第3項)
- 公益通報をしたことを理由とする解雇の禁止(公益通報者保護法3条)
以上に述べた事実が認められても,解雇は,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合は,その権利を濫用したものとして,無効とされます(労働契約法16条)。
客観的な合理的理由の存在
「客観的に合理的な理由を欠く場合」とは,解雇に値する事由に該当する事実を欠く場合をいいますが,従業員の行為が(1)の解雇事由に該当し,それを客観的に証明できる場合には,客観的な合理的理由は存在するといってよいでしょう。
一般的には,ア)労働者の労務提供不能,困難,不安定または適格性の欠如・喪失(労務信頼性の著しい欠如・喪失を含む),イ)労働者の規律違反の行為(重大な規律・秩序・勤務義務違反,重大又は反復の業務命令・職務遂行・守秘義務違反等),ウ)経営上の必要性に基づく事由(人員整理,合理化による職種・業務の消滅・減少等),エ)ユニオン・ショップ協定に基づく組合の解雇要求などがこれにあたります。
社会通念上相当と認められること
解雇理由が客観的かつ合理的なものであるとしても,さらに社会通念からみて労働者を企業から排除するに値するほどのものとは評価できない場合には,解雇は認められません。言い換えると,解雇が認められるためには,解雇理由が客観的に存在しても,それがクビにするのに値する程度のもの,解雇が社会通念上相当と認められることが必要です。
裁判所は,①であげたア)ないイ)の事由については,これらの事由が重大な程度に達しており,他に解雇回避の手段がなく,かつ労働者の側に宥恕すべき事情がほとんどない場合にのみ,社会通念上相当と認める傾向があるとされます。
従業員解雇するにはどのような手続が必要か(解雇の手続的要件)
従業員を解雇できる場合にあたるとしても,実際に従業員を解雇するには,以下にみるように,所定の手続を踏む必要があります。
就業規則等に定める解雇手続の履行
就業規則や労働協約が従業員を解雇する際の手続を定めている場合には,まず,その手続に従わなければなりません。
解雇予告手続の履行(予告除外認定を含む) 労基法20条
労働基準法20条1項は,「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」と定めており,従業員を解雇するには,30日前に予告するか,解雇予告手当を支払わなければなりません。
もっとも,同条項但書は,「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。」としており,この但書が定める事由に該当すれば,解雇の予告や解雇予告手当は不要となりますが,この但書が定める事由に該当するかどうかは,労働基準監督署長の認定を受けなければなりません。
手続不遵守の場合の解雇の効力
使用者が上記労基法所定の解雇予告手続の履行をせずに解雇した場合,最高裁判所は,その解雇は即時解雇としては効力を生じないが,使用者が即時解雇に固執する趣旨でない限り,解雇の通知後30日の期間を経過するかあるいは予告手当を支払ったときから解雇の効力を生ずるとしております。
但し,この場合,労基法20条の定める手続には違反しており,使用者は,労基法20条違反として処罰(6ケ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)される可能性があるので,要注意です。
(千賀守人)
以上、解雇の要件を見てきましたが、実際、個々のケースで解雇できるかどうかの判断にお悩みの場合、お気軽にご相談ください。